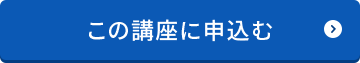〈紫式部〉は平安時代の三十六歌仙の一人に選ばれ、勅撰和歌集に58首も採られ、『源氏物語』の作者でもあるのに、本名も生没年も明らかではありません。その中で、わずか130首ほどですが『紫式部集』の短歌には、娘時代の友人とのめぐり合いや離別、越前守となった父と共に過ごした越前での一年間、夫宣孝との結婚、娘賢子の誕生、二年ほどでの夫との死別、失意の中での物語の執筆、宮仕えの現実と憂愁、世の無常などが、式部自身の言葉で詠まれています。式部は、幼くして母を失い、頼りにしていた姉も若くして亡くなって後は、妹を失った女友達と心を支え合った。物語に心を寄せ、同じ思いを有する友人を求めた。しかし、結婚も幸せとはいえず、夫の死後の宮仕えも、式部の願う場所ではなかった。そうした胸の内を、どのように歌に詠んでいるのかを読み解きながら、式部の心の遍歴を理解したい。
講座協力:(株)みらい応援・わくわくラボ(わくラボ)